まずは無料でご相談ください
アドバンストアイには大手上場企業から、中堅企業、小規模企業まで、さまざまな売上規模の会社のM&Aを手がけてきました。
まずはお気軽にご相談ください。

「会社を売るとしたら、いくらになるんだろう?」経営者なら誰もが、一度は考えたことがあるのではないでしょうか。
大切に育てた事業、大切な従業員や取引先。これらすべてを含んだ「会社の価値」を知ることは、引退、事業承継、成長戦略を考える上で欠かせない重要テーマです。
しかし、上場企業と違って、未上場の会社には客観的な「株価」がありません。
「では、未上場の会社の株価は『言い値』で決まるのか?」
決して、そんなことはありません。
未上場の会社の株価は、客観的なデータとロジックに基づいて決まります。会社の価値を適正に評価するための確立された方法が用いられるのです。
目次
テレビや新聞で日々報じられる上場企業の株価は、投資家の『買いたい』『売りたい』という需要と供給のバランスで決まります。
では、株式を公開していない未上場企業の場合はどうでしょうか。
未上場会社の株式売買は、M&Aや事業承継といった限られた場面でのみ行われます。買い手も特定の企業や個人など少数に限られるため、上場企業のような「時価」は存在しません。
市場での取引価格がないからこそ、未上場会社の株価算出には専門的な評価が必要です。財務状況、事業の将来性、市場環境など、会社の様々な要素を総合的に分析して価値を決めていきます。
・収益 :将来にわたって、どれくらいの利益やキャッシュフローを生み出す力があるのか
・資産 :会社が保有する土地・建物・現金などの純資産はいくらか
・成長 :独自の技術やビジネスモデルで、今後どれだけ成長が期待できるか
・無形資産:ブランド力、顧客基盤、ノウハウなど、数字に表れない強みは何か
・外部環境:業界は追い風か、向かい風か。競合の動向はどうか
これらの要素を総合的に分析し、企業の適正な株価を算出(企業価値評価)します。


企業価値評価(バリュエーション)とは、会社の様々な要素を分析して客観的な価値を算出することです。
複雑なように見えますが、実は代表的な3つの評価アプローチを使い分けるだけです。
絶対的な正解がないからこそ、『どの側面に注目して価値を評価するか』という視点の違いが重要になります。
会社の価値を評価する方法の一つに、将来性を重視するアプローチがあります。
現在の資産や利益だけではなく、その会社が将来にわたってどれだけの収益を生み出せるかに注目して評価を行います。
この考え方の代表的な手法として、DCF法があります。
■ DCF(Discounted Cash Flow)法
具体的には、以下のステップで企業価値を算出します。
・将来のキャッシュフローを予測する
→会社が将来にわたって生み出すであろう現金収入(フリー・キャッシュ・フロー)を見積もります。
・現在の価値に割り引く
→将来の100万円は、今の100万円より価値が低いため、「割引率」を使って今の価値に換算します。
・合計する
→各年のキャッシュフローの現在価値をすべて足し合わせて、会社全体の価値を算出します。
この「割り引く」という考え方は、「お金の時間価値」に基づいています。
「来年もらえる100万円」よりも「今すぐもらえる100万円」の方が、すぐに投資に回せる分だけ価値が高い、という当然の感覚を計算に反映させるのがDCF法の最大の特徴になります。
■ DCF法が特に有効なケース
DCF法は将来の成長性を重視するため、以下のような会社の場合は特に有効です。
・ITベンチャーやスタートアップ
→現在は投資が先行して利益が少ないものの、将来の急成長が期待される企業
・成長産業に属する企業
→業界全体が拡大しており、継続的なキャッシュフロー増加が見込める企業
この考え方は、不動産の価格査定と似ています。不動産の場合は「売りたい家の近所で、広さや築年数が似た物件がいくらで取引されたか」を参考にするように、M&Aでも、事業内容や規模が類似する会社が市場でどう評価されているかを基準にします。
この考え方の代表的な手法として、類似上場会社比較法があります。
■ 類似上場会社比較法
具体的には、以下のステップで企業価値を算出します。
・類似企業を選定する
→評価したい会社と、事業内容や規模、成長性などが似ている上場企業を複数社選び出します。
・評価の基準(倍率)を計算する
→選んだ企業の「時価総額が年間売上の何倍か」「企業価値が年間利益の何倍か」といった倍率を計算します。
・自社の価値を推定する
→計算した倍率の平均値を、自社の売上や利益にかけることで、企業価値を推定します。
この方法の最大の強みは、客観性と説得力の高さにあります。日々取引されている株式市場の明確なデータを基にするため、売り手・買い手の双方が納得しやすい価格の根拠となります。
そのため、多くのM&Aの現場では、交渉の初期段階で「この会社の価値はだいたいこのくらい」という相場観を把握するために広く活用されています。
この方法は、会社が保有する純粋な資産価値に着目して評価するアプローチです。
考え方は非常にシンプルです。「もし今、会社を精算(解散)した場合、最終的に株主の手元にいくら残るか?」を計算することで、企業の価値を求めます。つまり、企業を「解散価値」で評価する方法です。
この考え方の代表的な手法として、純資産価額法があります。
■ 純資産価額法
具体的には、企業の貸借対照表(会社の財産状況を示した表)から以下を計算します。
資産の総額 – 負債の総額 = 純資産
この純資産の金額を、そのまま会社の価値とする方法です。帳簿に記載された金額をそのまま使うため、「簿価純資産法」とも呼ばれます。
これら3つのアプローチは、どれか一つだけが絶対的に正しいというわけではありません。
実際のM&Aの現場では、会社の特性に応じて、これrなお方法を複数組み合わせ、多角的に分析するjことで、より実態に即した企業価値を導き出していきます。
この方法の強みは、計算がシンプルで客観的に理解しやすい点にあります。過去に蓄積された実際の資産を基にするためです。
算出される価値は、「この会社は少なくともこれだけの価値はある」という最低保証ラインを示します。そのため、以下のような場面で活用されます。
・M&Aの価格交渉で「最低価格」を把握する
・不動産や設備を多く持つ会社(不動産管理会社、製造業など)の基礎評価
複雑なプロセスを経て算出された会社の評価額は、そのまま最終的な売買価格になるわけではありません。
算出された企業評価額は、あくまで買い手との交渉のテーブルに載せるための「参考価格」や「基準点」として機能します。
最終的な売買価格は、この価格を基準に、お互いの様々な事情や目的を反映した交渉によって決定されます。
では、その交渉のテーブルでは、どのような要素が価格を変動させるのでしょうか。
これは、価格が評価額より高くなる最大の要因です。「シナジー」とは相乗効果のことで、M&Aでは「1+1が3にも4にもなる」効果を指します。
例えば、
・買い手の最新技術と売り手の強力な販売網を組み合わせて、売上が飛躍的に伸びる
・重複する管理部門を統合して、大幅なコスト削減を実現する
このような相乗効果が大きいほど、買い手は基準価格に上乗せしてでも買収したいと考えます。
売り手が「なぜ会社を売りたいのか」という理由も、価格に大きく影響することもあります。
例えば、以下のような急を要する事情がある場合は要注意が必要です。
・後継者が見つからない
・経営者の年齢や健康上の理由で、早急に事業承継したい
このような状況では交渉で不利になり、買い手から価格を下げられる可能性があります。
M&Aの交渉は、金銭の額だけで行われるわけではありません。売り手として、価格と同じくらい、あるいはそれ以上に重視したい条件があるはずです。
•「長年苦楽を共にしてきた従業員の雇用は、必ず守ってほしい」
•「先代から受け継いだ社名や、大切に育てたブランドは残してほしい」
•「引退後も、顧問として会社に残り、事業の引継ぎをサポートしたい」
こうした金銭以外の条件を買い手に受け入れてもらう代わりに、価格面で譲歩するといった合意点を探ることもあります。これも、最終的な価格を変動させる大きな要因です。
このように、最終的な売買価格は、論理的に算出された「評価額」を基準としながらも、売り手と買い手の「個別の事業」「将来への期待」、そして「金銭以外の条件」といった様々な要素が交渉によって調整されて決定します。


未上場会社の価値は、主に3つのアプローチで多角的に評価されます。
ただし、算出された評価額は交渉のはじまりにすぎません。最終的な売買価格は、シナジー効果による価格の上乗せ、売り手・買い手それぞれの事情、従業員雇用や社名存続などの非金銭条件を含めた交渉によって決まります。
このとき重要なのが、信頼できるM&Aの専門家に相談することです。
M&Aの専門家は、企業価値の正しい評価、交渉戦略の立案、複雑な手続きの管理に加え、経営者の想いを理解して買い手との橋渡し役を担います。
M&Aは経営者の人生における重要な決断であり、適切な知識と専門家のサポートが成功するためのポイントとなります。
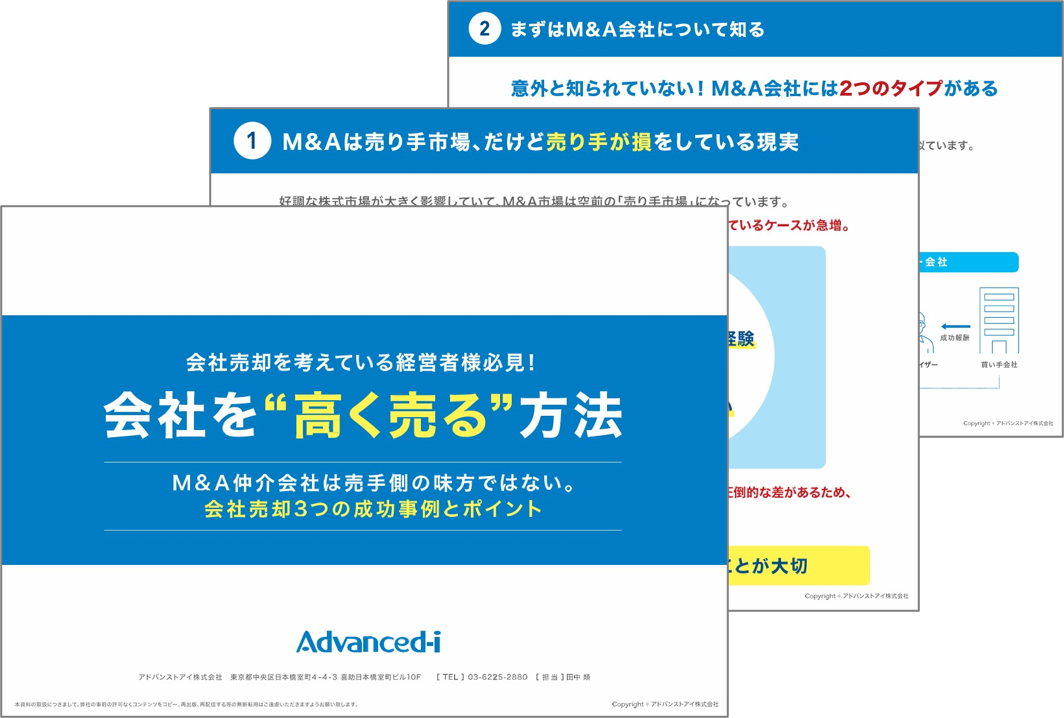
アドバンストアイには大手上場企業から、中堅企業、小規模企業まで、さまざまな売上規模の会社のM&Aを手がけてきました。
まずはお気軽にご相談ください。