まずは無料でご相談ください
アドバンストアイには大手上場企業から、中堅企業、小規模企業まで、さまざまな売上規模の会社のM&Aを手がけてきました。
まずはお気軽にご相談ください。

会社を売却するM&A。経営者にとって、これほど重大な決断はありません。
しかし、多くの経営者が売却後にこんな後悔をしています。
「もっと高く売れたはず…」
「こんな条件になるとは思わなかった…」
理由は明白で、立場が違えば、求めるものも違うので、M&Aに関わる関係者全員の違いが一致しないからです。
売り手は、できるだけ高く、良い条件で売りたい
M&A会社は、早く成約して手数料を得たい
買い手は、できるだけ安く、有利な条件で得たい
医療の世界では「セカンドオピニオン」が当たり前ですが、M&Aでも同じように、第三者の専門家に客観的な意見を求めることができます。
– 売却価格は適正なのか?
– 契約条件に不利な点はないか?
– 他にもっと良い選択肢はないか?
利害関係のない専門家が、あなたの立場に立って、重要な判断をサポートしてくれるのがM&Aのセカンドオピニオンになります。
今回は、後悔しないM&Aのために、M&Aのセカンドオピニオンの活用方法についてご紹介したいと思います。
目次
育ててきた会社を譲渡するM&Aは、経営者にとって重大な決断です。
最近ではニュースで話題になることも増えましたが、実際に「こんなはずではなかった」と売却後に後悔する経営者が少なくありません。
では、会社を売却した経営者はどんな後悔をしているのでしょうか。
■「正しく評価されていない…」
売却後、多くの経営者が企業価値評価について疑問を抱きます。
「M&A会社から提示された評価は本当に妥当だったのか」
「急成長している事業の将来性が十分に評価されているのか」
「独自の技術や顧客基盤が正しく価値に反省されているのか」
自社の価値が正しく評価されたのか、会社売却後にこの後悔を抱く経営者は少なくありません。
■「約束が守られない…」
最近よく耳にするのか、売却後も経営者保証が外されないケースです。
これは、M&Aによって会社の経営権を手放したにもかかわらず、元経営者が会社の債務に対する個人保証から解放されないという深刻な問題です。
事業から離れた後も、新経営陣の経営判断によって自身や家族の資産がリスクに晒され続けるという、理不尽な状況に置かれてしまいます。
主な原因としては、譲渡先企業の信用力が十分でないために金融機関が保証の解除に応じないケースや、M&Aの交渉段階で保証解除が明確な条件として盛り込まれていなかったケースなどが挙げられます。
■「従業員の雇用が守られない…」
売却条件に「従業員の雇用は守る」と入れていたにもかかわらず、M&A後に待遇が悪化したり、リストラの対象になったりすることもあります。
「あの時、もっと慎重に条件を確認していれば…」
「従業員を裏切ってしまった…」
従業員を守れなかったという後悔は、経営者にとって最もつらいものではないでしょうか。
■「急かされて決めてしまった…」
「今を逃すと次のチャンスはありません」
M&A仲介会社からこう言われ、十分に考える時間もないまま契約してしまうケースもよくあります。
会社を売ろうとしている経営者は、買い手が見つかった安心感や、早くこのプレッシャーから解放されたい気持ちで頭がいっぱいになっています。
そんな心理状態では冷静に判断できず、結果的に自分に不利な条件で解約してしまいます。
なぜ、このようなことが起こるのでしょうか。
売り手の経営者が置かれる状況には、2つの大きな問題があります。
問題① 圧倒的な知識・経験の差
・買い手やM&A仲介会社は、何度もM&Aを経験しているプロ
・一方、売り手の経営者にとっては、人生で初めての経験
・専門用語だらけの交渉の中、気づかないうちに不利な立場に立たされてしまう
問題② 誰にも相談できない環境
・M&Aは極秘に進められるため、役員や従業員にも相談できない
・「会社の未来」「従業員の生活」「自分の人生」という重大な決断を、たった一人で抱え込まなければならない
この2つの問題が重なることで、M&Aの失敗につながってしまいます。


M&Aで失敗しないために有効なのが、「セカンドオピニオン」です。では、M&Aにおけるセカンドオピニオンとは、具体的にどういうものでしょうか。
「セカンドオピニオン」と聞くと、病院での診療を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。担当医の診断に対して、別の医師にも意見を聞くことです。
医療の場合、自分の命や健康に関わる重要な判断を、より多くの情報をもとに選択するための患者の大切な権利です。
M&Aでも同じことが言えます。M&Aは、会社の将来と従業員の人生を大きく左右する重大な決断です。今、依頼しているM&A会社の提案内容が本当にベストなのか。
• 企業価値の算定は適正か?
• 買収候補先は最適か?
• 契約条件は妥当か?
このような内容を、別の専門家にチェックしてもらうことは、経営者として当然の権利であり、むしろ果たすべき責任と言えます。
セカンドオピニオンは、売り手の経営者が納得のいく決断をするために、主に3つの重要な役割を果たします。
① 提示された条件が妥当かチェックする
M&A仲介会社から提示された内容が、客観的に見て妥当なのかを検証します。
• 「この企業価値の評価額は適正か?」
• 「買い手から提示された条件に、売り手にとってのリスクはないか?」
こうした点を、専門的かつ中立的な立場で分析し、評価の根拠を分かりやすく説明します。
② 他の選択肢を提示する
現在のM&A会社が提案する戦略や候補先が、唯一の道とは限りません。セカンドオピニオンは、異なる視点から新たな可能性を提示してくれます。
• 「より良い条件を引き出せる別の買い手候補はいないか?」
• 「株式譲渡以外の方法(例・事業譲渡)は考えられないか?」
③ 判断材料を整理して、決断をサポートする
誰にも相談できず孤独な決断を迫られる経営者にとって、信頼できる相談相手の存在は何よりの支えです。セカンドオピニオンは、下記のようなサポートをします。
• 複雑な情報を整理し、重要な論点を明確にする
• 感情ではなく、客観的なデータと専門知識に基づいた判断材料を提供する
• 経営者が自信を持って最終決断できるよう、力強くサポートする
セカンドオピニオンを求める際は、相談相手の選び方が非常に重要です。主に以下のような専門家に相談できます。
① M&Aアドバイザリー会社・FA(ファイナンシャル・アドバイザー)
M&Aアドバイザリー会社は、依頼者の利益を最大化することを使命とします。売り手か買い手のどちらか一方の味方として働くため依頼者の立場に寄り添った客観的なアドバイスが期待できます。
② M&Aに詳しい弁護士・公認会計士・税理士
それぞれの専門分野から、具体的なアドバイスを提供します。
• 弁護士: 契約書などの法的リスクをチェック
• 公認会計士: 財務・会計の観点から評価
• 税理士: 売却後の税金など税務面からアドバイス
【最重要】完全に独立した専門家を選ぶこと
最も大切な注意点は、「今依頼しているM&A仲介会社と利害関係のない、完全に独立した専門家を選ぶ」ことです。
例えば、
• 仲介会社から紹介された専門家 → 中立的な意見が得られない可能性
• 自分で探した独立した専門家 → あなたの利益を最優先に考えてくれる
相談者の利益を第一に考えてくれる専門家を見つけることが、セカンドオピニオンを成功させる鍵です。
セカンドオピニオンの効果は、誰に相談するかで大きく変わります。会社の未来を託すに値する専門家を選ぶために、どんな点に注意すればいいのでしょうか。
ここでは、重要な3つのチェックポイントについてご紹介します。
セカンドオピニオンの専門家は、100%売り手の味方でなければなりません。
特定のM&A仲介会社や買い手候補と提携関係にあったり、紹介料を受け取っていたりする専門家では、中立的なアドバイスは期待できません。
• 特定のM&A仲介会社と提携関係にある
• 買い手候補から紹介料を受け取っている
• 他の関係者とつながりがある
相談者の利益を最大化することだけにコミットしてくれるパートナーを選びましょう。
M&Aは、会計・税務・法務などといった専門知識が複雑に絡み合います。それぞれの分野に精通していることはもちろん、それらを横断してM&Aプロセス全体を俯瞰できる知見が求められます。
また、自社が属する「業界」への理解も欠かせません。業界特有の商慣習や将来性を理解していなければ、企業価値を正しく評価することはできないからです。
これまでのM&A支援実績や、自社と類似する業種の支援経験などを確認し、確かな専門性と実績を持つ専門家かを見極める必要があります。
確認すべきポイント:
• これまでのM&A支援実績
• 自社と似た業種での支援経験
• 具体的な成功事例
どんなに優れた専門家でも、説明が難しくて理解できなければ意味がありません。専門用語を並べるのではなく、経営者の目線に立って、平易な言葉で丁寧に説明してくれるコミュニケーション能力は必須です。
また、M&Aは経営者にとって、合理的な判断だけでは割り切れない、感情的な側面も大きい取引です。
•「会社をどのような形で未来に残したいか」
•「従業員にどうなってほしいか」
こうした経営者の個人的な想いや不安に真摯に耳を傾け、心から寄り添ってくれる相手かどうか。初回面談では、専門性だけでなく、その人の人柄や自分との相性もしっかり確認することが大切です。
信頼できる専門家は、料金体系も明確です。
セカンドオピニオンにかかる費用は、M&Aが成立した時に支払う「成功報酬」ではなく、相談時間に応じたタイムチャージや、企業価値評価レポート作成などの作業単位での固定料金が一般的です。
相談を始める前に、必ず料金体系について詳しい説明を受け、見積書を提示してもらってください。「どこまでのサービスが料金に含まれるのか」「追加費用が発生するケースはあるか」「支払いのタイミングはいつか」などを事前に明確にしておくことで、安心して相談に集中することができます。


ここまで、後悔しないM&Aを実現するためのセカンドオピニオン活用法についてご紹介してきました。
会社の未来、そして従業員の人生を左右するM&Aは、経営者にとってまさに孤独な決断です。その重圧の中で、誰にも相談できずに一人で抱え込んでしまうことこそが、判断を誤る最も大きなリスクと言えるでしょう。
M&Aを進める中で、「本当にこの条件で良いのだろうか」「何か致命的な見落としはないか」といった胸のざわめきは、決して気のせいではありません。それは、一度立ち止まり、多角的な視点から冷静に現状を分析すべきだという、未来からの重要なサインなのです。
私たちは、単に売り手と買い手を繋ぐ「M&A仲介」ではなく、創業以来、徹底的にクライアントの利益を第一に考える「M&Aアドバイザリー」として、企業の未来づくりを支援してまいりました。もし今、少しでもご不安や疑問を感じていらっしゃるなら、まずは私たちにそのお気持ちをお聞かせください。
一つでも当てはまるなら、セカンドオピニオンを検討する価値があります。
• 提示されている株価(企業価値)が本当に適正なのか、客観的な評価が知りたい。
• 契約書に潜む、将来の表明保証違反などの隠れたリスクを洗い出してほしい。
• 現在の仲介会社が、相手方の意見ばかりを尊重しているように感じる。
• M&A後の統合作業(PMI)が具体的にイメージできず、成功する確信が持てない。
• そもそも、このM&Aが自社にとって最良の選択なのか、根本的な部分から相談したい。
私たちは、貴社の状況を丁寧にヒアリングし、第三者の専門家として公平な立場から最適な道筋をご提案します。
M&Aという重大な局面で、最高の決断を下すために。私たちの知見をぜひご活用ください。
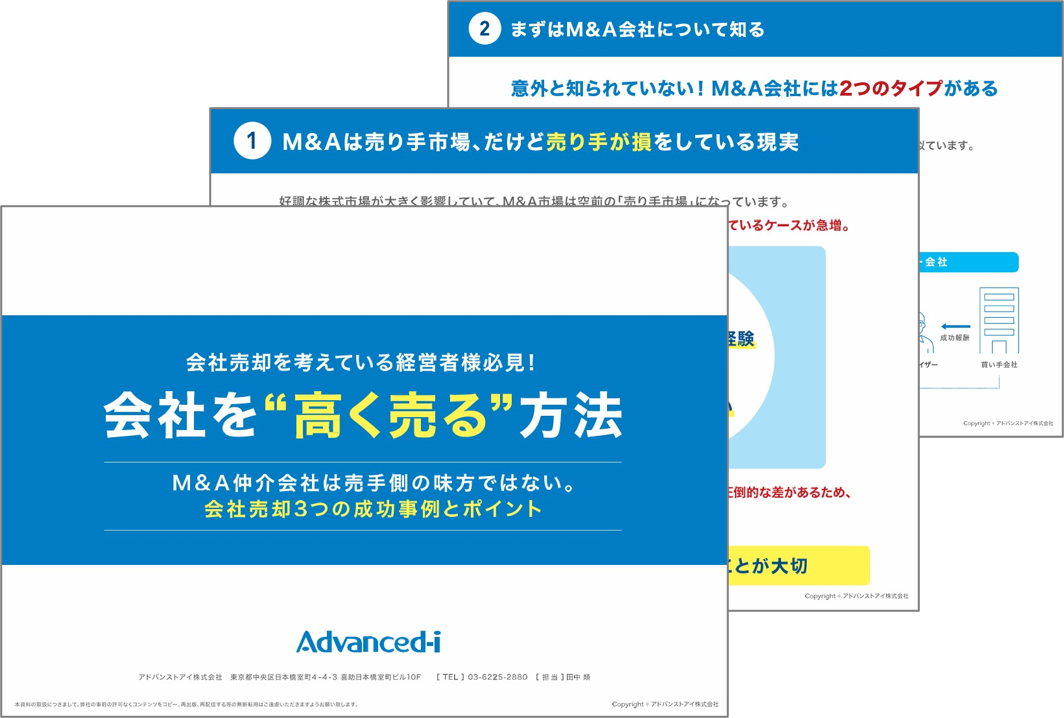
アドバンストアイには大手上場企業から、中堅企業、小規模企業まで、さまざまな売上規模の会社のM&Aを手がけてきました。
まずはお気軽にご相談ください。