まずは無料でご相談ください
アドバンストアイには大手上場企業から、中堅企業、小規模企業まで、さまざまな売上規模の会社のM&Aを手がけてきました。
まずはお気軽にご相談ください。

「うちは利益が出ているから大丈夫」
そう思っている経営者様ほど、M&Aで損をしてしまう可能性があります。
なぜなら、中小企業の決算書は節税のために利益を圧縮していることが多く、そのままでは企業の「本来の稼ぐ力(実力)」が買い手に伝わらないからです。
シリーズ第2回となる今回は、筋肉質な財務体質へと生まれ変わらせる「財務の磨き上げ」について解説します。
中小企業の決算書は、一般的に「節税」を意識して作成されています。しかし、M&Aにおいて買い手が最も注目するのは、税金を引いた後の最終利益ではありません。
買い手が知りたいのは、「その会社が本来持っている稼ぐ力(正常収益力)」です。
例えば、オーナー個人の裁量による経費や、親族への役員報酬、一時的な特別損失などが含まれたままでは、会社が本来生み出している利益が過少評価されてしまい、結果として譲渡価格の低下を招く恐れがあります。
適正な評価を得るためには、過去の決算書をそのまま見せるのではなく、非連続な費用や公私混同の経費を除外した「実態バランスシート・損益計算書」への引き直しが必要です。
私的な経費や、相場より高い役員報酬を標準化する
過去に一度だけ発生した修繕費や退職金などを取り除く
保有資産(不動産や有価証券)の実価を反映させる
この「財務の磨き上げ」を行うことで、買い手に対して「この会社を譲り受ければ、これだけの利益が確実に出る」という強い根拠を示すことができ、より有利な条件での成約へとつながります。


M&Aにおいて、企業の買収価格(株価)は、主に「その会社が毎年どれくらいの利益を出せるか(収益力)」を基準に算出されます。つまり、「利益が少ない=会社が安く買い叩かれる」ということです。
しかし、多くの中小企業経営者は、長年「いかに利益を減らして税金を安くするか(節税)」に腐心してこられたのではないでしょうか。皮肉なことに、この「行き過ぎた節税」こそが、M&Aの高値売却を阻む最大の敵となるのです。
まずは、損益計算書(P/L)に紛れ込んでいる「余分な贅肉」を削ぎ落とし、会社が本来持っている実力(正常収益力)を証明する必要があります。
オーナー企業によく見られる以下の経費は、買い手から見れば「事業に関係のないコスト」です。
これらを「本来は利益として残るはずのお金」として再計算(修正)します。
役員用の高級車: 事業に必須ではない高級外車などの減価償却費や維持費。
過大な生命保険: 節税目的で加入している高額な保険料。
私的な交際費: オーナー個人の飲食代や家族旅行費、ゴルフ代など。
これらを決算書上で「経費」として計上していると、見かけ上の利益が圧縮され、株価が低く算定されてしまいます。M&Aを検討し始めたら、これらの節税策はストップし、素直に利益を計上して納税する方が、結果的に手取りの売却益は大きくなるケースが多いのです。
また、オーナー社長自身の給与(役員報酬)も見直しの対象です。
もし、オーナーが相場より高い報酬(例:年間5,000万円など)を取っている場合、買い手はこう考えます。
「社長が退任した後、代わりの社長を雇えば年間1,500万円で済む。つまり、差額の3,500万円は本来、会社の利益だ」
このように、オーナーへの過剰な報酬を市場相場(実質コスト)に戻し、その差額を利益に上乗せすることで、企業の収益力は見違えるほど高く評価されるようになります。
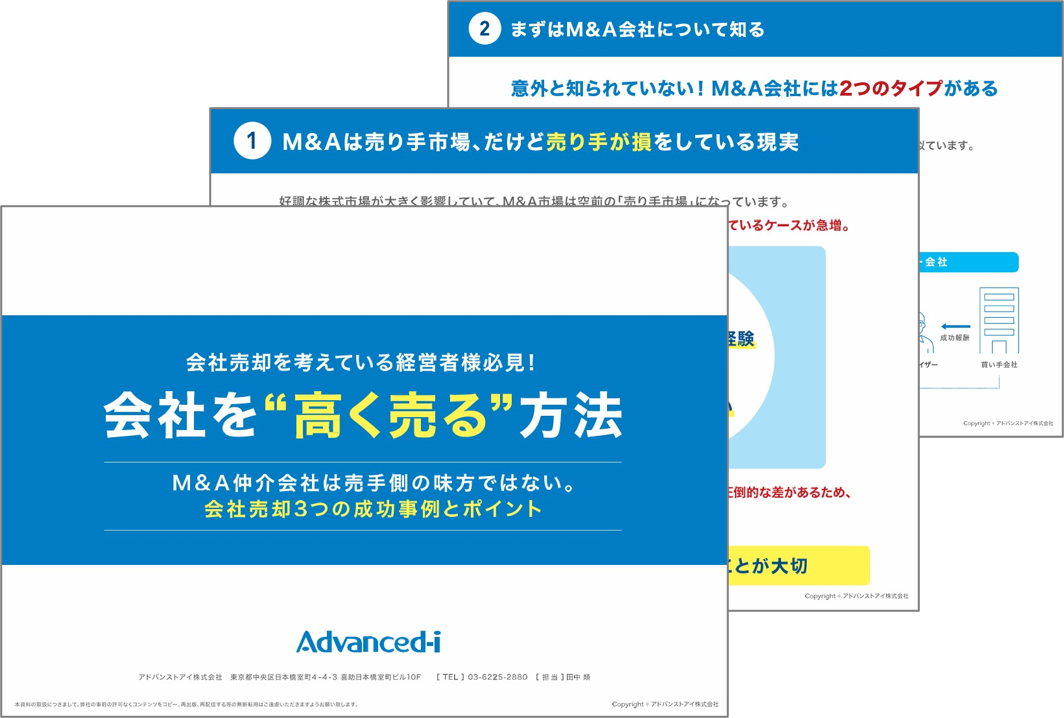
アドバンストアイには大手上場企業から、中堅企業、小規模企業まで、さまざまな売上規模の会社のM&Aを手がけてきました。
まずはお気軽にご相談ください。